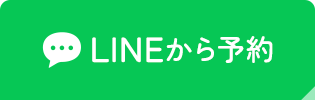膀胱炎について

膀胱炎とは、大腸菌などの細菌が尿道から膀胱に入り込んで増えることで、膀胱粘膜で炎症が生じた状態です。特に女性は、尿道が短く尿道口が膣内にあるため細菌が感染しやすく、男性に比べて膀胱炎の発症リスクが高いです。女性が生涯で一度は経験すると言われる身近な病気です。
症状
排尿時痛(特に排尿の終わり際)・頻尿・残尿感などの症状が突然起こります。下腹部不快感・血尿が出ることもあります。膀胱炎自体で発熱の症状は起こりませんが、膀胱内で増えた細菌が腎臓に広がると、腎盂腎炎によって38℃以上の発熱が起こります。
高齢の方では、排尿時痛や残尿感があまり出ず、頻尿の悪化のみが症状のこともあります。
検査・診断
問診と尿検査で診断することが基本です。
尿培養という尿の検査で、どのような菌が原因になっているか調べます。通常数日かかりますが、原因菌が抗生剤への耐性を持つか、また効果がある抗生剤は何かを確認します。
残尿検査や超音波検査は、複雑性膀胱炎(何かしらの原因によって膀胱炎を何度も繰り返す状態)などの病気の検査のために行います。
治療
大腸菌が膀胱炎の代表的な原因菌です。ばい菌を退治する抗生剤の内服で治療します。通常3-7日間の内服を行いますが、抗生剤の種類によって異なります。また、尿培養の結果で原因菌や抗生剤への効きやすさが分かれば変更や追加することもあります。症状をやわらげる漢方薬を使用することもあります。なお、症状が改善したからといって服用を中断すると、細菌がまだ残っていることもあり、治りにくくなったり、再発しやすくなったりする恐れがあるため、医師の指示にしたがって最後まで服用するようにしてください。
予防
細菌感染は単に細菌がいるから起こるのではなく、細菌数と体の抵抗力という2つの要素が複合することで起こります。尿が膀胱内に滞留時間が長くなると細菌が増殖しやすくなり、膀胱炎の発症リスクが高まります。長時間(3-4時間以上)尿を我慢することが多い仕事の方なども、3-4時間を目安にトイレに行きましょう。性行為の後に膀胱炎を発症しやすい場合は、行為の後に排尿することが大切です。さらに、免疫力が下がっていると、細菌感染する場合があります。ストレスや疲労をためないようにして、下半身を冷やさないようにしましょう。冷えなどが原因の場合、漢方が有効なこともあります。
1年で3回以上膀胱炎を繰り返す方は、細菌がしつこい場合や細菌がくっつくような結石がある、排尿障害で残尿があるなどの原因が考えられます。腹部超音波検査や残尿検査などで繰り返す要因がないか検査しますので、ご相談ください。