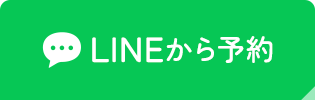尿失禁について

尿失禁(尿漏れ)とは、排尿をご自身の意思で制御できずに漏らしてしまう状態のことです。命を脅かす病気ではありませんが、生活の質(QOL)の低下をもたらします。解剖学的な特徴から女性の方が尿失禁の患者様が多く、最近の疫学調査では特に40代以上では女性で30〜45%、男性でも10%ほどが該当します。女性では、お腹に力が入った際に漏れる腹圧性尿失禁が多いですが、急な尿意で間に合わず漏れてしまう切迫性尿失禁もあり、両方の症状がある方もいます。男性の場合は前立腺肥大症の症状のひとつであることが多いです。
以下のように尿失禁の種類は多岐にわたり、治療法もそれぞれ違うため、問診や検査によって種類を特定した上で適切な治療をご案内いたします。
主な尿失禁の種類
腹圧性尿失禁
症状
咳やくしゃみ、運動の際に腹圧が上がり、膀胱が圧迫されて尿が漏れる種類のものです。発症原因は、尿道を支える組織や尿道を閉める筋肉の力が低下することだとされています。
男性の場合、前立腺肥大症や加齢による排尿括約筋(排尿の最後に尿を締める筋肉)の低下で起こることがあります。一方で、女性は解剖学的な特徴や、出産(経腟分娩)・加齢などによって骨盤底筋群の力が低下しやすいため、腹圧性尿失禁の発症率自体は女性の方が高いです。実際のところ、尿失禁に悩んでいる女性の半数程度が腹圧性尿失禁に該当すると言われています。
治療
行動療法
行動療法の治療効果は高いですが、長期的に続けていくことが重要です。
生活指導
以下によって、骨盤底になるべく負担をかけないようにします。
- ダイエットする(肥満の方に有効)
- 便秘を改善する(いきむ回数を減らすため)
- 激しい運動などを控える
- 重いものをなるべく持たない
骨盤底筋訓練
低下した骨盤底筋群の機能を改善する訓練です。
肛門、膣をぎゅーとしめるようなイメージの運動となります。運動の効果は1~3ヶ月で現れることが多いです。毎日続けることが大切であり、途中で止めてしまうと元の状態に戻ってしまいます。生活のリズムの中でうまく取り入れて継続しましょう。
骨盤底筋体操の動画はYouTubeにも様々なものがありますので、それらを見ながら取り組んでみることもお勧めします。
薬物療法
外尿道括約筋(排尿の最後に尿を締める筋肉)の収縮を増強されるβ2アドレナリン作動薬などを使って症状をやわらげます。漢方薬などが有効なこともあり、使用することもあります。
手術療法
行動療法や薬物療法では効果が不十分な場合に検討します。骨盤臓器脱(膀胱や子宮が下に垂れてしまう状態)をともなうことが多く、専門の婦人科や女性泌尿器科で、下垂した臓器を吊り上げる専門的な手術になります。
切迫性尿失禁
症状
急に我慢できないくらい激しい尿意を催し、漏らしてしまう種類のものであり、尿失禁の患者様の2割程度が該当します。過活動膀胱の症状の1つであり、膀胱が一時的に過剰に収縮することで生じます。
男性は前立腺肥大症の合併症として切迫性尿失禁が起こる場合があります。
治療
膀胱訓練
過活動膀胱による膀胱の過剰な収縮が続くのは1~2分ほどであり、長く続くことはほとんどありません。排尿後1時間以内に尿意を催した場合、2~5分程度で構いませんので排尿を我慢すると、一時的に尿意が収まることが多く、膀胱の容量を少しずつ増やしていくことができます。尿意が収まらない場合は無理に我慢せず、排尿してください。最終的に排尿を2~3時間我慢できるようになれば、日常生活への影響も軽微なものとなります。
尿が出にくいなどの症状が強い方は悪化することもありますので、無理には行わず受診してください。
骨盤底筋訓練
骨盤底筋を収縮させて、反射的に膀胱の収縮を抑える治療法です。主に腹圧性尿失禁に対して行われますが、切迫性尿失禁に対しても有効とされています。
薬物療法
以下のようなお薬を使った薬物療法が治療の基本となります。
β₃アドレナリン受容体刺激薬(ベタニス・ベオーバ)
膀胱の筋肉を緩め、膀胱容量を増やす効果があります。急な尿意を抑えて尿漏れも減らします。副作用は軽微なものが多く、高齢の方でも比較的安全に使用できることが多いです。
β2アドレナリン受容体刺激薬(スピロペント)
腹圧性尿失禁(お腹に力が入った際に漏れる)には、排尿の最後に尿を締める筋肉である外尿道括約筋の作用を強くするお薬を使用することがあります。
抗コリン薬(トビエース・ベシケアなど)
膀胱の過剰収縮を抑制する効果があります。様々な種類がありますが、薬により強さや持続時間が変わります。
便秘、口内乾燥、排尿困難などの副作用が起こることがありますので、注意しながら使用します。
前立腺肥大症治療薬(ハルナール・ユリーフなど)
男性で残尿感や尿の勢いが弱いといった他の症状を確認し、前立腺肥大症の場合は、症状や程度にあったお薬を使用します。前立腺肥大症治療薬だけでは、3-4割の方が尿失禁の症状が残るため、上記のβ₃アドレナリン受容体刺激薬、抗コリン薬などを追加することもあります。
溢流性尿失禁
症状
尿閉(尿が膀胱に溜まっていても出せない)の状態になると、満杯のコップに水を入れると水が少しずつ溢れるように尿が漏れる種類の尿失禁です。尿意はそこまで強くありませんが、広がった膀胱によって下腹部が膨らんで、チョロチョロと尿が漏れてきます。発症原因としては、前立腺肥大や膀胱の機能低下などが挙げられます。溢流性尿失禁では残尿が多く、尿路感染や腎機能障害も合併している恐れがあります。
治療
尿道から膀胱へ管を挿入し、尿閉をまずは解除します。そして安定して尿を出せる状態にした上で、原因に応じた治療を行います。
機能性尿失禁
症状
身体運動機能障害や認知症が原因でトイレ以外の場所で排尿してしまうタイプの尿失禁です。例えば圧迫骨折などでトイレまで間に合わずに漏れてしまう場合や、認知症の方で、トイレを認識できず他の場所で尿失禁になってしまうケースなどがあります。
治療
昨今、日本では高齢化が進行しており、機能性尿失禁はしばしばみられるようになっています。身体運動機能を改善するためのリハビリが重要ですが、中々リハビリで身体機能を回復することも難しいことが多いと思います。前立腺肥大症や過活動膀胱など他に尿失禁を悪化させる原因がないか調べ、あれば、治療をして少しでも尿失禁をやわらげるようにしていきます。β₃アドレナリン受容体刺激薬で尿失禁が減り、ご本人だけでなく介護される方の負担を減らすというデータもありますので、必要があればお薬など調整していきます。
混合性尿失禁
腹圧性尿失禁と切迫性尿失禁が合わさった状態です。尿失禁でお悩みの女性のうち3割程度が混合性尿失禁に該当します。
治療
患者様それぞれの尿失禁の状態に応じて、適切な治療を行います。
切迫性尿失禁の症状が重度の場合は、薬物療法が基本となります。
腹圧性尿失禁の症状が重度の場合は行動療法や薬物療法を基本としますが、効果が乏しい場合は手術療法も考慮します。
尿失禁に対して行う主な検査
問診

問診で失禁時の状況・失禁量・失禁回数を伺うことで、尿失禁の種類をある程度は特定することができます。尿失禁について話すことは恥ずかしいかもしれませんが、適切な治療を行うために詳細に教えて頂けますと幸いです。受診しやすい雰囲気を心掛けています。
検尿
同様の症状が起こる尿路結石・尿路悪性腫瘍(血尿が出ます)、尿路感染などの有無を調べます。
残尿検査
排尿後に残尿がないかを調べます。
尿流測定検査(ウロフロメトリー)
排尿の勢いを確認するため、検査用のTOTOのトイレでいつもと同じように排尿して頂く検査です。患者様へご負担はかかりません。次のような項目を確認し、他人と比べて排尿の勢いはどうか、弱い場合は原因が何なのかを調べます。排尿の機能を調べる検査です。
- 排尿時間
- 排尿量
- 平均尿流率(排尿の勢いの平均値)
- 最大尿流率(排尿の勢いが最も強い時の値)
腹部超音波検査(必要な場合に行います)
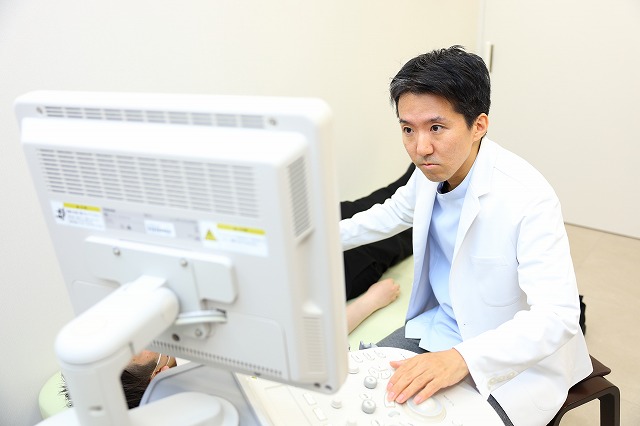 同様の症状が起こる他の病気の有無(がんや結石など)を確認するために行います。検査にあたっては膀胱内に尿が多く溜まっている状態が望ましいため、検査が終わるまでは排尿しないようにしていただきます。プローブという機器にゼリーを塗って下腹部に当て、検査を行います。女性の場合は必ず女性看護師が同席いたします。
同様の症状が起こる他の病気の有無(がんや結石など)を確認するために行います。検査にあたっては膀胱内に尿が多く溜まっている状態が望ましいため、検査が終わるまでは排尿しないようにしていただきます。プローブという機器にゼリーを塗って下腹部に当て、検査を行います。女性の場合は必ず女性看護師が同席いたします。
その他
別の病気を合併している可能性がある場合、必要な検査を追加で行います。