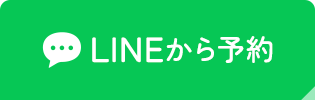過活動膀胱(OAB : overactive bladder)について
 過活動膀胱とは、急に生じる耐えられないくらい激しい尿意が出現して、日中や夜間の排尿回数が多くなったり(頻尿、夜間頻尿)する状態を表します。このような強い尿意が出現して、我慢が出来なくなると、結果として尿が漏れてしまうこともあります。
過活動膀胱とは、急に生じる耐えられないくらい激しい尿意が出現して、日中や夜間の排尿回数が多くなったり(頻尿、夜間頻尿)する状態を表します。このような強い尿意が出現して、我慢が出来なくなると、結果として尿が漏れてしまうこともあります。
このような「急に生じる耐えられないくらい激しい尿意」を尿意切迫感と言います。膀胱の過剰な収縮が急激に生じることであり、排尿をずっと我慢して生じる激しい尿意とは別物です。40代以上の14%程度(1,040万人程度)に見られる症状であり、年代が上がるほどその割合は上昇(70代以上で30%程度)するため、過活動膀胱でお困りの方は非常に多いです。
また、過活動膀胱になっている方の50%程度は切迫性尿失禁(我慢出来ず尿が漏れてしまう状態)を併発しており、さらにその50%に週1回以上の尿失禁が見られるとされています。尿失禁が起こるようになると、日常生活へ大きな悪影響が及び、生活の質(QOL)も大きく下がります。頻尿や尿漏れは我慢するものと考えられたり、恥ずかしさで受診にまでいたらないこと多いですが、外出を控えたり、仕事に支障が出たりするため、本来のいきいきとした生活に影響している場合は一度診察を受けてみましょう。
原因
過活動膀胱の原因は、神経因性(脳から膀胱に至る神経の異常)と非神経因性に大別されます。
神経因性過活動膀胱
脳梗塞や脳出血などの脳血管障害や、認知症やパーキンソン病などの脳障害、多発性硬化症や脊髄損傷などの脊髄障害が原因となります。これらの疾患によって、脳から膀胱に「排尿(尿を出す)」や「畜尿(尿をためる)」についての指令がきちんと伝達されず、急激に膀胱が過剰に収縮することで過活動膀胱になります。
非神経因性過活動膀胱
女性は加齢や出産によって膀胱などを支える骨盤底筋の筋力が低下するため、そこを通る膀胱に悪影響が及び、過活動膀胱に繋がる場合があります。
男性は加齢によって前立腺が肥大し、排尿障害に繋がります。このような状態が長年続くと膀胱に負担がかかり、膀胱の血流が悪化することで、過活動膀胱を発症する場合があります。
肥満(メタボリック症候群)は男女いずれにも共通する発症原因です。肥満によって全身の血管内皮障害や慢性炎症、自律神経系の亢進が起こり、過活動膀胱を発症するとされています。
他にも、原因不明の過活動膀胱もあります。なお、実際に現場で診察させて頂くと、かなりの方は明確な原因が不明で、加齢にともなって起こってくる状態の一つであることが大半です。
主な検査
症状を基に過活動膀胱の診断をするため、同じような症状が起こる病気の除外診断が求められます。
下部尿路炎症性疾患(ばい菌感染や尿の通り道に結石があり膀胱が刺激されて頻尿になるもの)
前立腺炎、膀胱炎、間質性膀胱炎、尿道炎、下部尿路結石
悪性疾患(がんが膀胱などを刺激して頻尿になるもの)
前立腺がん、膀胱がん
など
検尿

血尿や尿路感染などの有無を調べます。異常があった場合は別の病気を調べて治療することがあります。
残尿検査
膀胱の機能を評価します。自覚があまりなくても残尿が多くなっていることもあります。その場合は、更に詳しく調べます。また、内服の治療後も定期的にチェックが必要です。
その他
以下の過活動膀胱症状スコアを使って症状を評価します。
| 質問 | 症状 | 点数 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝起きてから寝るまでに何回排尿したか。 | 0 | 7回以下 |
| 1 | 8~14回 | ||
| 2 | 15回以上 | ||
| 2 | 就寝してから翌朝起きるまでに、排尿のために何回くらい目を覚ましたか。 | 0 | 0回 |
| 1 | 1回 | ||
| 2 | 2回 | ||
| 3 | 3回 | ||
| 3 | 急激に尿意を催し、我慢するのが困難なことがあったか。 | 0 | なし |
| 1 | 週に1回未満 | ||
| 2 | 週に1回以上 | ||
| 3 | 1日に1回程度 | ||
| 4 | 1日に2~4回 | ||
| 5 | 1日に5回以上 | ||
| 4 | 急激に尿意を催し、我慢できずに失禁したことがあったか。 | 0 | なし |
| 1 | 週に1回未満 | ||
| 2 | 週に1回以上 | ||
| 3 | 1日に1回程度 | ||
| 4 | 1日に2~4回 | ||
| 5 | 1日に5回以上 | ||
| 合計点 | 点 | ||
日本排尿機能学会 過活動膀胱診療ガイドライン作成委員会:過活動膀胱診療ガイドライン[第2版]、2015
診断基準
次の2項目いずれも該当する場合、過活動膀胱の診断となります。(他の病気が除外されていることが必要です)。
- 質問3:尿意切迫感スコアが2点以上
- 合計点数:3点以上
重症度判定
- 軽症:3~5点
- 中等症:6~11点
- 重症:12点以上
過活動膀胱の疑いがある方は、上記のスコアを使って症状を評価してみることをお勧めします。
また、生活に大きく影響する疾患のため、日常生活で具体的にどのような状況で症状が起こりやすいか、外出や仕事などどのような状況で困っていらっしゃるか問診でお聞きします(例えば、バス旅行に行けず困っている、お皿洗いで頻回に尿意があり困るなど)。
排尿日誌
昼間頻尿、夜間頻尿が多い場合、排尿日誌を記録して頂きます。
排尿日誌は1日に何回トイレに行き、毎回何ml排尿しているか、飲水量などがどれぐらいかを記載して頂き、分析します。
他にも必要な検査があれば、患者様の状態に合わせてご案内いたします。
治療
 治療は症状の程度によって異なります。生活改善や骨盤底筋体操などの行動療法をまず行います。軽症の方は行動療法だけですむこともあり、薬物治療が必要な方も、行動療法も一緒に行った方が効果があります。行動療法は治療ガイドラインでも勧められているものであり、過活動膀胱の改善に有効とされています。
治療は症状の程度によって異なります。生活改善や骨盤底筋体操などの行動療法をまず行います。軽症の方は行動療法だけですむこともあり、薬物治療が必要な方も、行動療法も一緒に行った方が効果があります。行動療法は治療ガイドラインでも勧められているものであり、過活動膀胱の改善に有効とされています。
| 治療方法 | 推奨グレード | |
|---|---|---|
| 生活指導 | 体重減少・運動・禁煙・食事アルコール・飲水指導・便秘の治療 | A/C1 |
| 膀胱訓練・計画療法 |
定時排尿 初期尿意を我慢する |
A |
| 理学療法 |
骨盤底筋運動 フィードバック療法 |
AB |
| 行動療法統合プログラム | 各治療法を並行して行う | A |
日本排尿機能学会 過活動膀胱診療ガイドライン作成委員会:過活動膀胱診療ガイドライン[第3版]、2022
生活指導
ダイエット
生活指導の中で強く推奨するとなっているのは「ダイエット」で、肥満の方が過活動膀胱を改善するためには有効とされています。しかし、分かっていてもダイエットはなかなか簡単にはできないことが多いため、他の治療を組み合わせて長い目で実行出来れば良いでしょう。
水分摂取などの調整
水分摂取やアルコールの摂取量が多く症状を悪化させていることも多くあります。また、TVの健康番組で飲水を勧められ、過度な飲水量になっていることもあります。
膀胱訓練
①初期尿意を我慢する
畜尿障害の改善のために実施します。過活動膀胱による膀胱の過剰な収縮が続くのは1~2分ほどであり、長く続くことはほとんどありません。排尿後1時間以内に尿意を催した場合、2~5分程度で構いませんので排尿を我慢すると、尿意が収まることが多いです。なお、尿意が収まらない場合は排尿してください。最終的に排尿を2~3時間我慢できるようになれば、日常生活への影響も軽微なものとなります。
②定時排尿
膀胱の容量を超えない範囲で、一定スパンで排尿する訓練をして頂きます。すぐにトイレにいくことが習慣になっている方では有効なこともあります。
理学療法
骨盤底筋運動
低下した骨盤底筋群の機能を改善することで骨盤底筋を収縮させて、反射的に膀胱の収縮を抑えます。主に腹圧性尿失禁に対する治療法ですが、切迫性尿失禁に対しても有効とされています。
おならを我慢するようなときにぎゅーと肛門を締めるイメージの運動となります。毎日続けることが大切であり、途中で止めてしまうと元の状態に戻ってしまいます。運動の効果は1~3ヶ月で現れるとされています。
薬物療法
以下のようなお薬を使った薬物療法が治療の基本となります。
β₃アドレナリン受容体刺激薬(ベタニス・ベオーバ)
膀胱の筋肉を緩め、膀胱容量を増やす効果があります。急な尿意を抑えて尿漏れも減らします。副作用は軽微なものが多く、高齢の方でも比較的安全に使用できることが多いです。
抗コリン薬(トビエース・ベシケアなど)
膀胱の過剰収縮を抑制する効果があります。様々な種類がありますが、薬により強さや持続時間が変わります。
便秘、口内乾燥、排尿困難などの副作用が起こることがありますので、注意しながら使用します。特に高齢の方では、他のお薬との飲み合わせで副作用が出やすくなることもありますので、必ず他のお薬を確認した上で、使用します。
漢方薬
高齢の方で副作用に注意しないといけない場合や、冷えなど別の症状が関係している場合などは漢方薬を使用します。
薬物療法はあくまでも症状をやわらげるお薬ですので、服用を中止すると元に戻ります。また、膀胱に尿が溜まるようになるとかえって残尿が多くなることがありますので、定期的に症状や残尿のチェックが必要です。