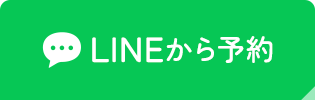前立腺がん
2023年のデータによると、前立腺がんは男性の中で最も発症者数が多いがんとなっており、その数は年間98,000人程度にも上ります。新たに前立腺癌と診断された患者様の数は40年で約5倍になっています。50代を過ぎると発症率が上がり、加齢に伴って発症者数は増加します。早期の段階であれば、一般的には進行が比較的ゆっくりで治療により他の癌に比べかなり良好な予後が期待できますが、進行すると骨やリンパ節に癌が転移しますので、早期発見が重要です。ただ、進行がんでも新規治療方法が次々と出てきているため、再発・転移の状態でも長期のコントロールが可能となってきています。
2025年時点では新たに前立腺癌と診断された方の約半数が75才以上のいわゆる高齢者になっています。高齢の方では進行がかなりゆっくりで経過をみるだけで良い方も多い一方、前立腺癌で亡くなる方も多くいらっしゃるため、それぞれ患者様の状態に合わせて検査、治療を考えていくことが重要になります。
症状
前立腺がんは基本的には自覚症状がないことが多いです。進行すると排尿困難や血尿の症状が起こります。また、リンパ節や骨に転移しやすく、リンパ節転移による下肢リンパ浮腫や骨の痛みなどの症状が起こる場合があります。
検査
PSA検査
PSAとは前立腺上皮細胞で生成されるタンパク質であり、PSA検査は前立腺がんの検査の中で最も簡単に行うことが可能です。年齢によって若干の差はありますが、一般的な基準値は4ng/ml未満が正常となります。しかし、前立腺炎や前立腺肥大、前立腺がんなどによって前立腺が刺激を受けるとPSAの数値が高くなることも多いため、間隔をあけて採血を行ったり、他の検査結果なども含め総合的にみて癌の疑いの有無を判断します。
直腸診
肛門から指を挿入して前立腺の触診をします。前立腺がんの場合、表面が凸凹で石のように硬い病変があれば確認できます。内側に潜むような早期の癌は分かりません。
超音波検査
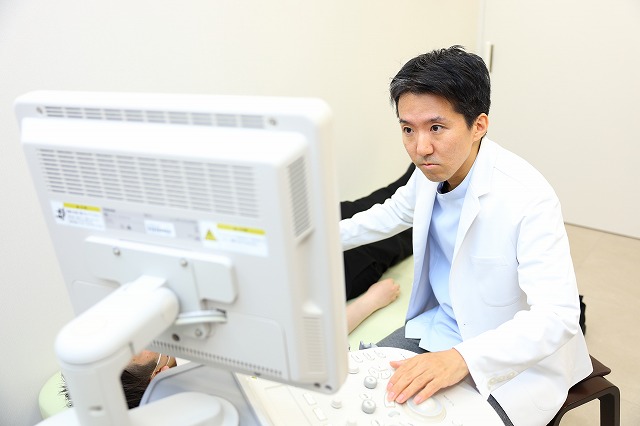 前立腺のサイズなどを調べます。前立腺肥大症でもPSAが上昇することがありますので、前立腺肥大症も合わせて確認します。
前立腺のサイズなどを調べます。前立腺肥大症でもPSAが上昇することがありますので、前立腺肥大症も合わせて確認します。
MRI検査
近年、MRIによる前立腺がんの診断の精度が非常に高くなっています。従来からの撮影方法に加え、2種類以上の撮影方法を組み合わせることで、非常に小さいミリ単位の病変も分かるようになってきています。前立腺癌の疑いが強ければ、MRIで怪しいと思われる部位を生検で調べます。一方、非常に小さく癌と断定出来ない場合や癌でも小さすぎてすぐには進行しないと考えられる場合などは経過をみていくこともあります。
確定診断
上記のような検査で前立腺がんの疑いがある場合、次のような検査を行って確定診断します。
前立腺針生検
超音波で前立腺を確認しながら細い針を使って前立腺組織をいくつか採取し、顕微鏡でより詳しくしらべます(病理検査)。前立腺組織の一部を採取しているだけですので、小さながんなどの組織を採取できない場合もあります。そのため、この検査でがんが見つからなくても、定期的にPSA検査を受けて数値が高い場合は再度組織検査をします。
画像診断
CT/MRI
前立腺がんの広がりや転移しているかどうかを調べます。
骨シンチ
骨転移しているかどうかを調べます。
治療
生検で採取した組織の悪性度(がんの顔つき)と画像検査での前立腺癌の広がり(いわゆるステージ)に加え、患者様の状態に応じて以下のような治療を行います。
監視療法
前立腺癌が前立腺内部にとどまっており、生検での組織の悪性度がそこまで高くない場合に慎重に経過をみていき、治療をした方が良い段階になってくるようであれば治療を考えていくというものです。定期的にPSA検査やMRI検査、前立腺針生検を受ける必要があります。
手術療法
前立腺がんが前立腺内部に留まっていて、余命が10年以上期待できる場合は、以下のような方法で前立腺全摘術を実施します。入院が必要になり、ある程度手術に耐えられる方が対象です。術後、尿失禁や性機能障害(勃起不全)が生じます。尿失禁は1年後にはかなりの割合の方が改善してきます。性機能障害は勃起の神経を残す手術方法もありますが、癌の状態にもよります。
開腹手術
臍下から恥骨上縁までを切り開き、手術を行います。
腹腔鏡下前立腺全摘術
腹部の数ヶ所にカメラや鉗子を入れるための穴を開け、炭酸ガスを使って腹部を膨張させて手術を行います。開腹手術よりも出血が起こりづらく、術後も早期に回復できます。熟練した術者ではロボット支援手術と遜色ありません。
ロボット支援前立腺全摘術
手術用ロボットを操作し、腹腔鏡手術を行います。繊細な手術操作が可能で、出血が少なく抑えられ術後の回復が早い、尿失禁などをより早期から改善できるなどのメリットがあります。
放射線療法
前立腺に放射線を当てて癌を治療します。
照射方法は、組織内照射(前立腺の内側から当てる)と外照射(外から当てる)がありますが、病院によって異なります。外照射の場合、外来通院で治療が可能で、近年、より狭い範囲に正確に照射できるようになっています。高齢の方でも治療が可能です。前立腺周囲がただれて刺激されることがあるため、血尿や頻尿などが生じることがあります。
薬物療法
ホルモン療法
前立腺がんは男性ホルモンの影響で増えるため、男性ホルモンを抑える治療を行います。ホルモン療法はがんを取り除くのではなく、がんの成長を抑制することが目的です。放射線治療や手術を行えない方、高齢者、転移している方が対象となるほか、放射線治療の前後に行うこともあります。
去勢抵抗性前立腺がん
去勢抵抗性前立腺がんとは、ホルモン療法を長期的に続けるうちに段々と効き目が薄くなり、前立腺がんが進行してしまった状態のことです。この状態でも効果がある新しいタイプのホルモン剤などが近年使用可能になっており、予後が改善してきています。
化学療法
転移している前立腺がんや去勢抵抗性前立腺がんに対して、化学療法(抗がん剤)を行う場合もあります。
膀胱がん
 膀胱に生じるがんを総じて膀胱がんと呼びますが、そのうち9割程度が尿路上皮に生じる尿路上皮がんです。痛みは生じずに血尿が出たことをきっかけに受診される方がほとんどです。
膀胱に生じるがんを総じて膀胱がんと呼びますが、そのうち9割程度が尿路上皮に生じる尿路上皮がんです。痛みは生じずに血尿が出たことをきっかけに受診される方がほとんどです。
症状
痛みのない血尿が出現し、進行すると排尿困難や排尿時痛などの症状が起こります。発症初期は痛みが生じないことがほとんどで、血尿が出ることも少ないです。そのため、すぐに受診できずにがんが進行してしまうこともありますので、注意が必要です。
検査
検尿
血尿のチェックや、尿細胞診によってがん細胞の有無を確認します。
超音波検査
膀胱に尿が溜まった状態で膀胱壁を調べます。腫瘍ができていると、膀胱壁が不規則に隆起していることが分かります。また、尿管や腎臓への影響の有無も併せて調べます。
膀胱鏡検査
 尿道から膀胱にカメラを入れて、膀胱内部の状態を調べます。膀胱がんはブドウの房のような形をしていることが多く、病変の場所やサイズを観察します。
尿道から膀胱にカメラを入れて、膀胱内部の状態を調べます。膀胱がんはブドウの房のような形をしていることが多く、病変の場所やサイズを観察します。
CT検査
膀胱がんが転移しているかどうかを検査します。
MRI検査
膀胱腫瘍がどれくらいの広がりをしているか、リンパ節に転移していないかを調べます。
治療
手術療法
がんの進行度合いに応じて以下のような治療を行います。
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt)
内視鏡によって腫瘍を取り除きます。膀胱がんが発見された場合に最初に行う手術であり、患者様にあまり負担がかからないという特徴があります。取り除いた病変から、がんの深さ、癌の悪性度(顔つき)を確認することができます。浅い癌で悪性度が高くない場合は、この手術だけで経過観察になります。がんの範囲が広い場合や顔つきが良くない場合は、再発の予防としてBCG(結核の予防ワクチン“BCG”と同じもので結核菌の毒力を弱めた製剤です)を外来で6-8回ほど週1回膀胱内に注入します。術後も尿検査、腹部超音波、膀胱鏡などの定期チェックが必要です。
膀胱注入療法
膀胱がんは非常に再発しやすいため、手術直後にマイトマイシンC、アントラサイクリン系抗がん剤などを膀胱に注入することで、再発防止を図ります。前述したBCG膀胱内注入は術後退院してから外来で行う治療です。
膀胱全摘術+尿路変更術
TUR-Btでがんが深い部分(筋層以上)に浸潤していることが確認された場合に実施する手術です。膀胱を全摘出し、尿の出口を新たに腸管などで作成し、おへその横付近のストマから尿を出すようにします。大きな手術になります。腸管などを使って代用膀胱を作ることもあります。開腹手術と腹腔鏡下に行う方法があり、近年ロボット支援下の腹腔鏡下手術も施設によっては行われています。
放射線療法
がんが深い部分(筋層以上)に浸潤しているけれども、膀胱全摘術のような大きな手術が高齢や他の病気で出来ない場合に選択肢となります。化学療法と組み合わせて行うことが多いです。
化学療法、免疫チェックポイント阻害剤
化学療法は、画像診断や手術で膀胱の外にがんが転移していることが分かった場合、全身治療として実施します。または、がんが深いけれども手術が出来ない、または希望されない際にも放射線療法と組み合わせて行います。近年、免疫チェックポイント阻害剤という新しい種類のお薬が登場し、進行している膀胱がんでも抑えられることもあります。