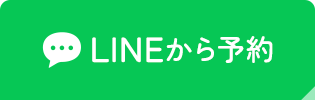尿が出にくい・勢いが弱い
排尿障害の症状は多岐にわたります。腹圧排尿(いきまないと排尿できない)・排尿困難(尿意があっても排尿しづらい)・尿線途絶(排尿中に尿が途切れる)・尿勢低下(若い時よりも尿の勢いが弱い気がする)などが代表的です。
腎臓で生成された尿は尿管を通り膀胱に溜まります。膀胱内の尿量が200-400mlほどになると、膀胱壁の伸展刺激が大脳皮質の排尿中枢に伝達されます。次に排尿中枢からの信号により膀胱が収縮して膀胱の外に尿を押し出し、膀胱の出口と尿道が広がることで排尿が完了します。脊髄の自律神経(交感神経・副交感神経)も関係し、実際はかなり複雑です。
尿が出にくくなる原因は、尿路の通過障害と膀胱の収縮障害に大別されます。通過障害の主な原因は男性では前立腺肥大症であり、膀胱収縮障害の主な原因は男女いずれも神経因性膀胱となります。
尿が出にくい(排尿困難)原因
前立腺肥大症(男性)
前立腺はクルミくらいの大きさの男性特有の器官であり、膀胱のすぐ下で尿道を囲むように位置しています。
また、前立腺は尿道付近の内腺と、内腺を囲むようにある外腺から構成されており、前立腺肥大症とは内腺が肥大する疾患のことです。
男性ホルモンなどの影響で前立腺が肥大するとされており、基本的に加齢に伴って肥大が進んでいきます。
肥大によって尿道の抵抗や圧迫が増えると、排尿困難・残尿感・頻尿などの症状が起こります。尿が通るトンネルの内側が狭くなると尿が出にくくなるのがイメージしやすいと思います。
前立腺がん(男性)
前立腺がんは中高年の男性が発症しやすい疾患です。
男性ホルモンが発症に影響するとされており、加齢や遺伝、脂肪や生活習慣(蛋白質の取り過ぎ)などがリスク因子とされています。
前立腺がんは前立腺肥大症とは異なり、前立腺の周りで起こりやすく、発症初期は自覚症状が少ないことがほとんどです。
排尿困難などの症状は、前立腺癌がある程度進行して、尿の内側にまで及んでくると出現します。前立腺肥大症と前立腺癌は基本的には別の病気ですが、前立腺肥大症に前立腺癌が潜んでいることもあるため、PSA(前立腺特異抗原)という採血を行うことで癌かどうか調べます。
尿道狭窄
尿道狭窄とは、何かしらの原因で傷ついた尿道が治る途中で、尿道が繊維化・瘢痕化して内腔が狭窄した状態のことです。
尿道の内腔が狭窄することで、排尿困難などの症状が起こります。尿道の外傷、内視鏡など尿道内で操作する医療行為、クラミジアや淋菌感染などによる尿道炎などが原因として挙げられます。
尿道狭窄の重症度に応じて治療法は異なります。軽症の場合は、ダイレーターという尿道拡張用の管を使って徐々に尿道を広げたり、内視鏡で尿道を切開することで尿道を広げたりします。重症の場合は、狭窄している尿道を取り除いて正常な尿道同士を繋げたり、頬の粘膜などを使って尿道を再建する尿道形成術を行ったりします。
神経因性膀胱
脊髄や脳などの疾患で排尿を制御する神経で異常が生じ、膀胱で尿を溜める機能や排尿機能に支障をきたした状態です。排尿困難は、膀胱を収縮される筋肉が弱くなり、膀胱の筋肉が緩くなるため、十分に尿が出し切れず生じます。腰椎椎間板ヘルニアや脊髄損傷など脊髄の疾患、パーキンソン病や脳梗塞など脳の疾患、直腸がん・子宮がんなど骨盤内の腫瘍の手術や糖尿病による末梢神経の障害などが原因として挙げられます。残尿が非常に多い前立腺肥大症の場合、長期間膀胱に負担がかかりなることがあります。また、膀胱出口の圧力を上げるお薬、膀胱収縮力を低下させるお薬、総合感冒薬、精神安定剤などの服用中のお薬によって、神経因性膀胱のような症状が起こる場合もあります。
原因疾患によって治療法は異なりますが、軽症であれば、膀胱の収縮を促すお薬や膀胱の出口の筋肉を開きやすくするお薬などを使った薬物療法を行います。薬物療法効果が薄い場合や程度が強い場合は、尿路管理のために尿道留置カテーテル法(膀胱に管を入れて尿を出す)や清潔間欠的自己導尿(ご自身で細い管で1日3-4回尿を抜く)を行います。しっかりと膀胱から尿を出して、尿路感染を防ぐことや、腎機能を守ることが必要です。
前立腺炎
前立腺炎は、男性特有の前立腺に何かしらの原因で炎症が生じる疾患です。
炎症の種類は、急性・慢性かによって区別されます。
症状は、急性の場合は排尿困難や排尿時痛、悪化すると高熱などが起こり、慢性の場合は下腹部・鼠径部・会陰部の違和感、排尿時の違和感や痛みなどが起こります。
骨盤臓器脱(女性)
骨盤臓器脱は女性ならではの疾患であり、子宮・直腸・膀胱などの骨盤の中の臓器が次第に降下して膣の外に出た状態のことです。降下する臓器に応じて、子宮脱・直腸脱・膀胱脱と言われています。
通常、これらの臓器は骨盤底筋群によって支えられていますが、加齢や出産に伴って骨盤底筋群が弛緩すると、徐々に降下していきます。症状としては、違和感・尿漏れ・頻尿・排尿困難などが挙げられます。膀胱脱だけでなく、子宮脱でも程度が強いと、膀胱も影響されて尿漏れや排尿困難などが出現します。残尿が多くなると膀胱の機能も低下します。
立位で下垂が強くなり、症状が悪化するため、座ったままの生活が多くなり、日常生活に影響を及ぼしてしまう方もいらっしゃいます。子宮などが脱出している感じがあり、排尿困難などもあれば、一度調べる方が良いでしょう。
治療法はペッサリーという膣内装具の挿入や骨盤底筋訓練による保存的治療もありますが、重度の場合は手術を行います。
尿道カルンクル
尿道の出口に生じる良性腫瘍であり、閉経後の中高年の女性が発症しやすいです。
血流が多く、疼痛や尿道からの出血を訴えて受診する場合があります。血豆のような見た目です。腫瘍が小さければ症状は乏しいですが、かなり大きくなると排尿困難の症状が起こる場合があります。良性のため大概は切除は不要で軟膏などの処置を行いますが、疼痛や出血が激しい場合や排尿困難の原因になる場合は手術で切除します。
排尿困難が長引く場合
病気によりますが、排尿困難が長引き、排尿できない状態が続くと膀胱の中に大量の尿が蓄積し、尿意を感じるのに排尿できない尿閉が起こります。尿閉が進むと、膀胱内の尿が腎臓に逆流して腎臓が膨張する水腎症が起こる場合もあります。初めは軽い症状だったのが、尿閉にまでなるとかなり辛いです。排尿しづらい、もしくは排尿できないといった場合は、なるべく早めに当院までご相談ください。
排尿しづらい場合の治療
検査などで排尿しづらくなっている原因を特定し、原因に応じた適切な治療法をご案内いたします。
詳しい治療法は原因疾患についての解説をご確認ください。
緊急性が高い場合は、導尿(尿道の出口から細いカテーテルを入れて、膀胱の中の尿を出す)を行います。