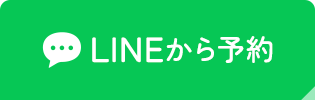頻尿
 1日8回以上排尿する方や、就寝後に排尿で2回以上起きる方は、頻尿になっている疑いがあります。ただし、1日の排尿回数が8回以下の場合も、ご自身で排尿回数が多いと思う方は頻尿に当てはまります。
1日8回以上排尿する方や、就寝後に排尿で2回以上起きる方は、頻尿になっている疑いがあります。ただし、1日の排尿回数が8回以下の場合も、ご自身で排尿回数が多いと思う方は頻尿に当てはまります。
夜間頻尿とは、就寝後に排尿で1回以上起きなければならない状態のことです。加齢に伴い夜間の排尿回数は増え、睡眠不足になって日常生活にも影響を及ぼす可能性があります。また、転倒の原因になる、介護者の負担増大につながることもあるため、QOLに大きな影響があります。
頻尿の代表的な原因
「膀胱の容量低下」「尿量の増加」「心理的要因」など原因は多岐に渡り、いくつかの原因が重なっていることが多いです。
膀胱の容量低下
膀胱の容量が150~200ml以下になると、尿量に変化はなくても排尿回数が増加します。膀胱内で使える容量が低下するケースがあります。神経因性膀胱や前立腺肥大症によって起こります。前立腺肥大症が長年存在すると膀胱に負担がかかり、膀胱の筋肉が“固く”なり膀胱容量が低下し、頻尿になることは多いです。
膀胱の過敏性
膀胱が過敏になり、尿量が少なくても急激に尿意を感じ、我慢することが困難になります。これは、膀胱からの信号が脳に過剰に伝わるためと考えられています。そのため、一度の排尿量が減って、頻尿を引き起こします。急激な我慢できない尿意で頻尿になるのが、いわゆる過活動膀胱の状態です。
残尿量の増加・排尿障害
膀胱を収縮させる神経の異常によって膀胱内の尿を全て排出できなくなり、残尿量が増加します。しかし、尿は絶えず生成されているためすぐに尿意を催すようになり、頻尿に繋がります。残尿量の増加は、前立腺肥大症などによって起こります。また、糖尿病によって膀胱の神経に異常が起こっている場合や、脳梗塞などの脳血管障害によって膀胱の収縮力が下がり、残尿量が増えて頻尿に繋がります。神経因性膀胱と言われる状態で、通常の頻尿を抑えるお薬で残尿が増えて悪化することもあるため適切な診断治療が必要です。
尿量の増加
1回の排尿量が150~200mlと普通でも、頻尿に悩まされている方は少なくありません。これは尿量の増加が原因であり、例えば、水をたくさん飲んだり、利尿作用のある飲み物(コーヒーやお茶など)やお薬を飲んだりすることによっても起こります。水分をたくさん飲んでいなくても、夜間の排尿回数が多い場合は、通常は夜間に分泌される体内の水分を調整するバソプレッシンというホルモンの分泌が加齢とともに低下し、尿がしっかりと濃縮されずに尿量が増加していることがあります。
心理的要因・ストレス
尿道や膀胱に問題はなく尿量も普通であるにもかかわらず、頻尿になる場合があります。これには心理的要因が影響しているとされています。大事なテストやスポーツの大会の際に緊張して頻尿になることは、どなたにでもあることです。しかし、こうした状況下ではないのに頻尿が慢性化する場合があり、日常生活への悪影響も懸念されます。
頻尿の症状が現れる代表的な病気
頻尿の症状が現れる病気は複数あり、治療法もそれぞれ異なります。
膀胱などの尿の通路で細菌感染が起こり膀胱炎などを発症して頻尿になることがあります。
また、膀胱がんや尿路結石など膀胱を刺激する病気で頻尿になっていることもあります。
こうした疾患による頻尿は急激な症状が起こることが多いですが、高齢の方では、症状がはっきりとしないこともしばしばあります。
また、骨盤臓器脱や子宮筋腫、前立腺肥大症などが原因で、尿道が圧迫されて頻尿になることもあります。このような疾患が原因となる場合は症状が少しずつ現れるため、受診される時点では発症して時間が経っていることもあります。
さらに、椎間板ヘルニア・脳卒中・糖尿病など膀胱を動かす神経に支障をきたす病気が原因で膀胱が過敏になり頻尿になる場合もあります。
神経性頻尿 (膀胱神経症)
膀胱で炎症などの異常は起こっていないものの、緊張やストレスが原因で頻尿になる状態のことです。1回の排尿量が少なくなることで頻尿になりますが、日常生活に悪影響が及ぶ場合はなるべく早めに当院までご相談ください。
膀胱炎
尿道から細菌が入り込み、膀胱粘膜で炎症が生じることで頻尿になります。睡眠不足や疲労が溜まっている時など免疫力が低下している際に発症しやすいため、注意が必要です。また、女性は体の構造上の問題で男性よりも尿道が短いため、膀胱炎の発症リスクが高いとされています。
急性膀胱炎は早めに治療を受ければ早期回復が期待できますが、放置すると腎盂腎炎などに発展して入院加療を要する可能性があります。こうした状態にならないようにするため、なるべく早めに専門医を受診してください。
過活動膀胱
膀胱内の尿量が少なくても膀胱が過剰に収縮し、急激な尿意を催すことで頻尿になります。尿漏れや失禁をともなうこともあります。加齢にともなって生じることが多いですが、脳梗塞など他に膀胱の神経に影響する病気によって起こる場合もあります。泌尿器科で専門的な治療を受けることで症状をやわらげることが出来る可能性がありますので、お困りの方は一度当院までご相談ください。
前立腺肥大症
前立腺は男性の膀胱のすぐ下にあり、尿道を取り囲むように存在しています。加齢に伴って大きくなった前立腺によって膀胱が圧迫されると、頻尿や尿の勢いが弱まる、残尿感などの症状をきたします。夜間頻尿の大きな原因のひとつです。悪化すると尿閉(排尿できなくなる)が起こる可能性もあります。なお、前立腺がんでもこれらの症状が起こりますので、前立腺癌のチェックも基本的には必要になります。
骨盤臓器脱 (性器脱)
女性の骨盤低筋群という筋肉・靭帯は、膀胱・子宮・直腸などの臓器を支える重要な役割を担っています。しかし、出産、加齢などにより骨盤底筋群の筋力が低下すると、これらの臓器が膣から脱出する骨盤臓器脱が起こることがあります。膀胱が脱出すると、頻尿や排尿困難、突然の尿意、尿漏れなどの泌尿器症状が現れます。重いものを持つ仕事に就いている方はお腹に力が入りやすいため、なりやすいです。また、便秘や肥満も骨盤臓器脱を引き起こす原因となりますので、注意が必要です。骨盤を鍛える体操やお薬による治療がありますが、重度の場場合は手術が必要になることもあるため、一度当院までご相談ください。
糖尿病
糖高血糖状態が慢性化すると、尿として排出される水分量が増加し、多飲多尿の状態となります。糖尿病の神経障害によって、膀胱の中の尿を全て排出できず頻尿になることもあります。尿検査で尿糖が出て無自覚の糖尿病が発見されることもしばしばあります。
膀胱がん
膀胱に生じるがんによって膀胱の容量が下がったり、がん自体が膀胱を刺激して頻尿になります。
頻尿の治療
基本的に薬物療法を行いますが、各患者様の頻尿の程度・原因によって適切な治療法をご案内いたします。
薬物療法
頻尿の原因を特定することが非常に大切です。尿検査では、尿の中に血が混ざっていないか、膿が出ていないかなどを調べます。また、排尿後に膀胱に尿が残っていないかを超音波検査などで確認します。残尿が多い場合は、その原因に応じたお薬をお出しします。また、残尿が少ない場合は、β受容体刺激薬(尿道を締め付けて排尿回数の減少や尿漏れ防止作用がある)や抗コリン薬(膀胱の収縮抑制作用がある)を処方します。
頻繁にトイレに行きたくなる方は当院までご相談ください
飲み物を飲み過ぎているだけの場合もありますが、深刻な病気によって頻尿になっている可能性もあります。男性は前立腺肥大症、女性は膀胱炎によって頻尿になりやすいとされています。当院では、各患者様の原因に応じた治療を提案させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
夜間頻尿
 夜間頻尿とは就寝後に排尿で1回以上目を覚ます状態のことであり、加齢がともに発症しやすいです。夜間頻尿により、睡眠の質が悪化し、日中の眠気をもたらし、仕事や生活に大きな影響を及ぼします。さらには、転倒や骨折を引き起こし生命予後にも関連するとの報告もあります。2023年の本邦の疫学データでは、男女とも尿に関して最も困っている症状が夜間頻尿でした。様々な原因が重なって夜間頻尿になりますが、主には膀胱の容量が少なくなる(膀胱容量の減少)、夜間に尿が多くなる(夜間多尿)、睡眠障害などが関係しています。原因がひとつであることは少なく、重なっていることが多いため、原因に応じた治療を組み合わせて行うことが多いです。
夜間頻尿とは就寝後に排尿で1回以上目を覚ます状態のことであり、加齢がともに発症しやすいです。夜間頻尿により、睡眠の質が悪化し、日中の眠気をもたらし、仕事や生活に大きな影響を及ぼします。さらには、転倒や骨折を引き起こし生命予後にも関連するとの報告もあります。2023年の本邦の疫学データでは、男女とも尿に関して最も困っている症状が夜間頻尿でした。様々な原因が重なって夜間頻尿になりますが、主には膀胱の容量が少なくなる(膀胱容量の減少)、夜間に尿が多くなる(夜間多尿)、睡眠障害などが関係しています。原因がひとつであることは少なく、重なっていることが多いため、原因に応じた治療を組み合わせて行うことが多いです。
夜間頻尿の原因
夜間多尿
糖尿病
糖尿病による神経の障害で膀胱容量が低下することがあります。また、糖尿病のコントロールがうまくされていない場合は、尿量が多くなり(多尿)、最終的に夜間頻尿に繋がることもあります。糖尿病の検査を受けていない方が夜間頻尿で受診され、検査で糖尿病が初めて判明することもあります。糖尿病によって様々な合併症をきたす恐れもありますので、なるべく早めに当院までご相談ください。
高血圧・心不全
夜間頻尿の原因として心不全や高血圧が関係している可能性があります。夜中に血圧が上がると、夜間尿量が増加します。また、心不全によって心機能が下がっている方は、就寝中に心臓へ水分が戻ることで血流が増加し、夜間尿量の増加にも繋がります。夜間の尿量が日中と比べて多いかどうか排尿日誌という1日の排尿記録を記載して頂き、調べることがあります。塩分摂取に気をつけ、血圧の管理をしっかり行うことが重要です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)
睡眠時無呼吸症候群とは、就寝中に無呼吸・低呼吸が頻発する病気です。心臓に負担がかかるため、心臓が大きくなり、心臓としては自分の負担を少しでも減らすため、尿の量を増やすホルモンを出します。結果として尿の量が多くなり、夜間頻尿となります。睡眠時無呼吸症候群自体が高血圧、糖尿病などの生活習慣病と関連しているため、これらの疾患も相まって更に症状が出やすくなります。明らかにいびきが頻回で、夜間頻尿もある方は一度ご確認ください。睡眠時無呼吸症候群の治療をすることで夜間頻尿が軽快する方もいます。
その他
健康のためと思い過度な飲水をされ、原因のひとつになっている方もいます。また、加齢ともに、本来は夜間に尿の排泄を抑えるホルモン(抗利尿ホルモン)の分泌が低下して、夜間に尿量が多くなることがあります。
膀胱畜尿障害
膀胱畜尿障害とは、前立腺肥大症、過活動膀胱などによって膀胱の神経が敏感になり、膀胱の容量が低下することで夜中に尿意を催して起きてしまう状態のことです。
前立腺肥大症
膀胱の下で尿道を囲むように位置している前立腺が大きくなり、膀胱や尿道が刺激を受けると尿意を催して排尿します。更に、前立腺肥大症があると膀胱の負担になり、筋肉が固くなるため、膀胱の容量が小さくなります。薬物療法を中心に治療します。
過活動膀胱
過活動膀胱とは、加齢などが原因で、排尿筋を適切に制御できない状態のことです。尿量が少ないのに激しい尿意を催す・残尿感がある・頻繁にトイレに行きたくなるといった症状がよく起こります。はじめに問診で原因疾患の有無を確かめます。原因疾患があればその治療を優先して行い、それと同時に薬物療法や膀胱訓練、生活習慣の改善なども行います。原因疾患がないことが多いため、その場合も、同様の治療を行います。
睡眠障害
就寝中に頻繁に起きてしまうことで夜間頻尿になる場合があります。眠りが浅いからトイレに起きるのか、尿意で刺激されるから起きてしまうのか、どちらが先かは明らかではありませんが、にわとり卵と同じで互いに関連しあっています。加齢にともなって眠りが浅っていることが原因としては多いですが、睡眠時無呼吸症候群や精神疾患、眠りにくくなる薬剤などが影響していることもあります。アルコールやカフェインも睡眠障害の一因になっている方もいます。
夜間排尿の診断
問診を行い、症状が始まったタイミングや程度について詳しく確認します。そして、尿検査・尿流量検査・超音波検査などを行って、正しい診断を行えるようにします。男性の場合は日中の頻尿や残尿感など他の症状も伴っていることが多いため、前立腺肥大症検査を行います。可能な方は、排尿日誌という何時にどの程度排尿しているか記録して頂くとより詳しく調べることが出来るため、記載方法などをご案内しています。
夜間頻尿の治療
夜間頻尿の要因は膀胱の容量低下だけでなく、睡眠障害や加齢など多岐にわたります。はじめに医師より夜間頻尿の原因となる要因をご説明し、患者様とご相談しながら治療を行っていきます。
多尿・夜間多尿に対する治療
飲水についての指導
就寝前の水の飲み過ぎは控えてください。また、利尿作用があるカフェインやアルコールについても、夜間頻尿の方は取り過ぎないようにしてください。
運動療法
夕方から夜にかけて運動することで、下半身に蓄積した水分が血管に戻ったり、汗として身体の外に出たりするため、夜間に尿意を感じづらくなります。夕方の散歩やスクワットなどがおすすめです。竹踏みでも効果があるという報告があります。
薬物療法
抗利尿ホルモンや利尿薬を使った薬物療法によって、尿量をコントロールします。しっかり検査を行い、経過を定期的にみれば比較的安全なお薬ですが、副作用が起きることもありますので、使用可能か医師と相談してください。
膀胱畜尿障害に対する治療
薬物療法が中心となりますが、原因疾患に応じて使用するお薬は様々です。男性の場合は前立腺肥大症、過活動膀胱のお薬を使用することが多く、女性の場合は過活動膀胱のお薬を使うことが多いです。お薬によっては膀胱に尿が溜まるようになり、今度は尿が出しにくくなったり、口の渇きなどの副作用が起こることもあるため、特にご高齢の方は慎重に経過をみながら薬を使用していくことが望ましいです。
睡眠障害に対する治療
睡睡眠障害によって夜間頻尿になっている場合、まず、生活習慣や睡眠環境の見直しも併せて行います。例えば、高齢の方では、就寝してから起きるまでの時間が長くなり過ぎて、浅い睡眠になり、夜間に起きてしまう方もいらっしゃるため、適切な睡眠時間を再検討します。
生活改善だけでは難しい場合には、睡眠薬を使用することがあります。